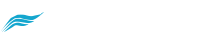気分障害の治療について
気分障害の治療は、患者さん個々の症状や生活環境に合わせたアプローチが基本です。まずは、専門医による綿密な診断を実施し、抗うつ薬や気分安定薬といった薬物療法、さらに認知行動療法などの心理療法を組み合わせた治療計画を策定します。また、治療効果の向上と再発防止のため、生活習慣の見直しや支援体制の強化も重要な要素となります。本ページでは、気分障害の治療について、薬物療法と精神療法の観点から解説します。
気分障害の薬物療法
気分障害の薬物療法は以下の薬を単独であるいは組み合わせて用います。
抗不安薬
気分障害の不安や不快気分(いらいらなど)を和らげるのに良く使われるお薬です。ベンゾジアゼピン系抗不安薬(デパス、ソラナックス、ワイパックス、レキソタンなど)が代表的な薬です。安全性が高くて、比較的即効性で良く効くのですが、依存性があるので注意を要します。すなわち毎日連用すると、効きにくくなり、量が増えて、その状態で急に中断すると、不安や不眠、イライラや焦燥感などの禁断症状が出ることです。
そのために患者さんは抗不安薬を急に止めると、禁断症状としての不安や焦燥感が出現して、病気がまだ治っていないと思い、また服用を続けざるをえない状態になります。使う場合は、頓服として投与したり、必要最小限にしたり、充分効果が出た後は、徐々に減らすべきです。
その他、タンドスピロン(セディール)や抗ヒスタミン作用のあるアタラックスも抗不安薬として使われます。
また睡眠導入剤として広く使われている薬(アモバン、マイスリー、ロヒプノール、ハルシオン、ベンザリン、レンドルミンなど)も同じような構造式を持った同じ仲間の薬です。
抗うつ薬
SSRIとSNRIがうつ病治療の第一選択として広く使われます。
SSRI
SSRIとは選択的セロトニンの再取り込み阻害薬のことですが、セロトニン神経系のセロトニントランスポーターに作用して、シナプス間隙のセロトニンの量を増やすことによって、回り回って抗うつ作用を発揮します。日本ではジェイゾロフト、パキシル、ルボックス、レクサプロが市販されています。
同じSSRIと言っても作用が微妙に違うため、どの抗うつ薬が一番良いかは、長年の経験によって処方しますが、使ってみないとわからないというところもあります。
SSRIおよびその他の抗うつ薬
SNRI(セロトニンとノルアドレナリンの再取り込み阻害剤)現在トレドミン、サインバルタが市販されています。
抗うつ薬としてその他に三環系抗うつ薬(アナフラニール、トリプタノールなど)、四環系抗うつ薬(テトラミド、ルジオミール、テシプールなど)、およびレスリン、アモキサンなどがありますが、これらは現在では、第一選択薬が効果がなかった場合の第二選択薬であり、また第一選択の薬が効果が不十分な場合に作用を増強する形で追加して使います。
また比較的新しい抗うつ剤としてミルタザピン(商品名、リフレックス/レメロン)も使われるようになっています。抗うつ作用、抗不安作用ともSSRIとは違う薬理作用であり、通常の抗うつ薬で効果がない場合でも効果がある場合があり、またSSRIに追加する形で使うことも多いです。ただし眠気などの副作用がはじめは強いため、注意する必要があります。また欧米ではすでに発売されて定評のあるブブロピオンなどの抗うつ薬も近々発売されると思います。
気分調整薬
リチウム、バルプロ酸、カーバマゼピン、ガバベンチン、ラモトリジンなど元来リチウムは躁状態の特効薬ですが、長期使用による毒性、すなわち腎機能障害や甲状腺機能障害を考慮して、以前ほど安易に使われることは少なくなりました。
かわりに抗てんかん薬として使われているバルプロ酸、カーバマゼピン、ラモトリジンなどが双極性障害に使われるようになりました。
これらは最初は双極性障害の躁状態の治療薬でしたが、気分調整薬として躁状態でないときも服用することで気分の安定が得られることが知られるようになってきました。
特にラモトリジン(ラミクタール)は双極性障害のうつ状態に対して効果があり、最近よく使われるようになっています。ただしスティーブン・ジョンソン症候群または皮膚・粘膜・眼症候群とも言われる重篤なアレルギー反応が出現する可能性があり、注意が必要です。
非定型抗精神病薬
これらは元来統合失調症の薬ですが、双極性障害の躁状態にも効果があり、欧米では保険適応が取れています。また双極性障害のうつ状態にもある程度効果があります。特に双極性障害のうつ状態に対してはSSRIと組み合わせて使うと効果があるようです。
オランザピン(ジプレキサ)、クエチアピン(セロクエール)、リスペリドン(リスパダール)、アリピプラゾール(エビリファイ)などがあります。
特にジプレキサとエビリファイは双極性障害の躁状態に対して保険適応がとれています。
精神療法
気分障害の精神療法としては気分や感情に焦点を当てた認知行動療法が有名です。その中でもA.T.Beckが創始した認知療法は、うつ病などの気分障害に効果があることが実証されています。認知療法で大事なことは、いくつかありますが、中でも思考と感情と行動が相互に連関していることを身をもって体験することにあります。例えば1時間のセッションなら、その1時間の中で気分を憂うつにするような考え方を変えたり、別考え方を探したりという作業によって抑うつ気分が改善することを体験してもらうことにあります。

よくある質問
- 治療にどれくらい時間がかかりますか?
- 治療期間は症状の重さや個人差によりますが、軽度の場合は数週間、中~重度の場合は数ヶ月の継続的な治療が一般的です。治療は段階的に効果が現れるため、継続して専門医の指導を受けることが大切です。
- 薬物療法と心理療法はどちらが効果的ですか?
- 多くの場合、薬物療法と心理療法は併用することで相乗効果が得られます。患者さんの状態に合わせた最適な治療計画は、専門医が丁寧に検討・提案いたします。
- 治療中に注意すべき点は何ですか?
- 治療中は、定期的な診察と医師とのコミュニケーションが不可欠です。自己判断で治療を中断したり変更したりせず、医師の指導のもとで生活習慣の見直しやストレス管理にも努めることが求められます。
- 副作用について教えてください。
- 薬物療法には副作用が生じることもありますが、ほとんどの場合は軽度であり、医師が適切な薬の調整や対策を行います。副作用や疑問があれば、すぐに医師に相談するようにしてください。
初診予約について
当院では、初診の方※は完全予約制となっております。初診のご予約はすべてお電話にて承っておりますので、受診をご希望の方は、下記の電話番号までお気軽にご連絡ください。
※初診の方…初めて当院を受診される方、もしくは最終受診より1年以上経過している方
気分障害の診断分類
気分障害とは、日常的な感情の浮き沈みとは異なり、長期間にわたって心のバランスが崩れ、生活に支障をきたす状態を指します。
下記ページにて、気分障害の診断分類について段階的に分かりやすく解説しています。